子どもたちのことは本当に大切に思っているし、のびのび育ててあげたい気持ちはあります。
…が、気持ちがあっても「毎日仏のような対応」や「子どもの気持ちに常に寄り添うこと」は難しい!
今日は、そんなわたしのイライラとの付き合い方(模索中)についてお話ししたいと思います。
もともと直情型の人間なわたし
幼い時から、良い感情も悪い感情もダダ漏れなわたし。
「腹が立つ」と感じれば不機嫌を他人へぶつけたこともあるし、
「めちゃめちゃ嬉しい!」ことがあれば、それもダダ漏れ。
歳を重ねていろんなことを経験するにつれ、「感情をストレートに態度に出しすぎることは良くないな」と気がつき、意識して出さないようになりました。
これは、大きく変わったのは子供が産まれてから。
また別の記事で書きたいのですが、3回の妊娠・出産、現在進行形の育児の中で、周りから心ない言葉をかけられたり、感情が揺さぶられることは多々ありました。
ですが、全部にいちいち反応していてはこちらの身が持たないし、何より時間の無駄だと気がつきました。
そう気が付いてからは、仕事中や友達との関係の中では、余程のことがない限り負の感情を表に出すことはなくなりました。
ただ、そううまくはいかないのが「対子ども」の関わりのときです。
わたしが子どもたちにイライラする理由
いろんな理由があって、子どもたちに対しては毎日…本当に、毎日、1日のうちに何度もイライラしています。
わたしが彼女たちにイライラするのはどんな時なのかについて、考えてみました。
短い時間の中で、何度も同じことを注意しなければならない時
髪を食べない、ご飯を食べるときは肘をつかない、人の話を聞くときは体を向けて目を見る、歯ブラシを咥えて歩かない…
これは、ほとんど毎日子どもたちに注意することです。
1日に何回も言っているのに、なぜだか一向に直りません。
「今、この時」を生きている子どもたちには、「さっきも言ったけど」が通用しないことは頭では理解しています。
ですが、わたしも感情ある人間です。同じことを何度言っても響かない様子だと、イライラしてしまうのです。
予定外の行動で、こちらの計画を乱される時
ママになって思うことは、「育児は、看護師業務以上に多重課題である」ということ。
常に、自分のこと、子どもたちのこと、家事をするために頭で計画を立てて遂行していかなければなりません。
ただでさえ過密スケジュールの中、
ママーお茶こぼした!
ママー保育園の巾着袋がない!
ママーおやつ食べたい!
もう、頼むからわたしの計画を乱さないでくれ!!と、イライラ。
わかってます。予想外のことが起きるのが育児。そして、子どもらしさなのも。
だけど、ママにも感情はあります。イライラするのです。
こちらが疲れている時に起こる事件
毎日仕事に育児に家事に…現代のママは基本的にいつも疲れていることでしょう。
身体的な疲れ、精神的なストレスがある時は、感情の制御が利かなくなることがわたしは多いです。
そんな中、また上記のような「ママ!ママ!の嵐」が起こると「もぉーーー知らんがな!💢」と爆発することもあります。
わたしが子どもたちにイライラする大きな理由は、以上3点です。
できれば、こちらも怒りたくない。疲れるし、感情的になっても何の意味もないことが多いから。
だけど、怒ってしまう。つらいですね。
アンガーマネジメントとは?
最近よく耳にする、「アンガーマネジメント」とは何なのか?について調べてみました。
怒らないことを目的とするのではなく、怒る必要のあることは上手に怒れ、怒る必要のないことは怒らなくて済むようになることを目標としています。
アンガーマネジメントとは? | 簡単にわかる目的と効果的なやり方
怒りの感情とうまく付き合うための心理トレーニングです。「怒らない方法」や「怒りを抑える方法」ではなく、怒りに任せた衝動的な言動をコントロールし、建設的に表現することを目的としています。
アンガーマネジメントとは?怒りの感情をコントロールする6秒ルールや実践方法 | 組織開発・人材育成 |ALL DIFFERENT株式会社
要するに、怒りの感情をそのまま表現するのではなく、冷静になって然るべき方法で表出する方法というところでしょうか。
うまく怒りの感情を付き合っていくことを目的とした心理トレーニングだそうです。
アンガーマネジメントの実践
いろいろ調べた結果、次のようなことが多くのサイトで紹介されていました。
これについて、育児中にも効果的であるか、実践可能かについて考えていきたいと思います
深呼吸をする
これはわたしはよくやります。
つい、感情的になってひどい言葉を言いそうな時や、カッとなっている!と自分で気づいた時に実践。
怒りのピークからは少し感情は落ち着きます。
が、自分がこの状態になっているときは、子どもの方もかなりヒートアップして感情が昂っています。
なので、一定の効果はあるけれど、その後は結局言い合いになることが多いです。
アンガーログをつける
これは、自分の手帳につけています。なるべく、感情が揺さぶられてすぐにつけるようにしています。
これも一定の効果があるかと思います!
自分の怒りのクセや傾向を知ることができると、「あ、このままいくと爆発するな」と会話の中で気づけるようになります。
一時期は、これでかなり感情的に爆発することを避けられていました。
が、長女が成長して口が達者になってきた今…新しいフェーズに突入し、怒りの傾向がわたしも長女も変わってきて、試行錯誤中です。
6秒ルールを実践する
6秒ルールとは、怒りを感じた時に6秒数え、怒りのピークをやり過ごし、理性的にのるための時間です。
これは実践してみましたが、わたしはあまり効果を感じませんでした。
なぜなら、子どもに対して6秒待ってる間に、次の事件が起きるから。
例えば…ご飯を食べないことを何度も注意しているのに、食べたくない野菜で遊び始めたところで怒りのピークを感じたとします。
「やめて」とだけ伝え、6秒を数え出すと、今度は子どももイライラしてコップを倒す。
それもグッと飲み込んでまた数えるけど、そのうちに空になったコップをわざと落とす…
はい、もう、6秒待てませんでした…
使いどきを間違えなければ効果的なルールかもしれませんが、常に動きが止まることのない子どもが相手では少し難しいかな、と感じます。
思考を止める
これは、一旦怒りの対象から物理的に距離を取り、そのことへの思考を止め、気分転換をすることのようです。
これは育児中にはかなり難しい。
特に未就学児の間は目の届かないところに置いておくわけにもいかないので、実践するのは難易度が高めだと感じます。
誰かが怒り狂い、誰かが泣き叫ぶカオスの中で意識を別の場所へ飛ばせるようになれば、できるかも。
わたしには今世では難しいそうです。
「べき」思考を手放す
これは実践できました。今もやっています。
わたしの手放した「べき」思考は、以下の通りです。
まだまだたくさんの「べき」を、ママになってからの6年間で手放してきました。
「こうあるべき」という考え方は、あればあるだけ生きづらくなり、自分を縛り付けることになります。
みんなそれぞれに事情があり、状況は違います。
性格も違えば、物事のキャパも違う。みんなが一様に「こうあるべき」なんてことは、実はそんなに多くありません。
そのことに気づけて、ずいぶん生きやすくなりました。毎日が楽しくなる!
「べき」思考を手放すことは、子育てにおいてはかなり効果的だとわたしは考えています。
子育て中にオススメなアンガーマネジメントの実践
子育て中は、子どもが小さいうちは特に「目を離すこと」が難しい状況にあります。
「一旦そばを離れること」も可能ではあるけれど、存在をシャットアウトすることは難しい。
それから、「今、この時」を生きている子どもたちとの関わりの中で、「無の数秒間」を作り出すことが難しい場合も多い。
そのため、わたしがオススメするアンガーマネジメントの実践方法は、
この3点です!
また、目を離すことは難しいけれど、耳から好きな音楽やラジオを聞くことは可能な場合はあります。
イヤホンをして、音をシャットアウトする。これも効果的だと、助産師さんからは教えられました。
たまには1人時間を持ちましょう
毎日、子育てお疲れ様です。本当に、わたしたち頑張っていますよね😌👍
日々の怒りのコントロールはもちろん必要ですが、たまには誰かに子どもをお願いして、1人時間を持ちましょう。
保育園の制度を利用してもいいし、パパや祖父母に頼ってもいい。
一つ言えることは、ママの精神的な幸福度が育児や家庭環境に良い影響を与えることは間違いありません。
「子育て」や「家事」、「仕事」から解放されて、自分を労る時間も大切にしたいですね😊
最後に
アンガーマネジメントできない三姉妹ママの、できないなりの考え方、いかがでしたか?
知識としてわかっていることと、実践できるということは違います。
それでも、無知でいることはよくない。
そして、少しでも勉強した知識を行動に移せるように、日々努力していきたいなと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*’▽’)
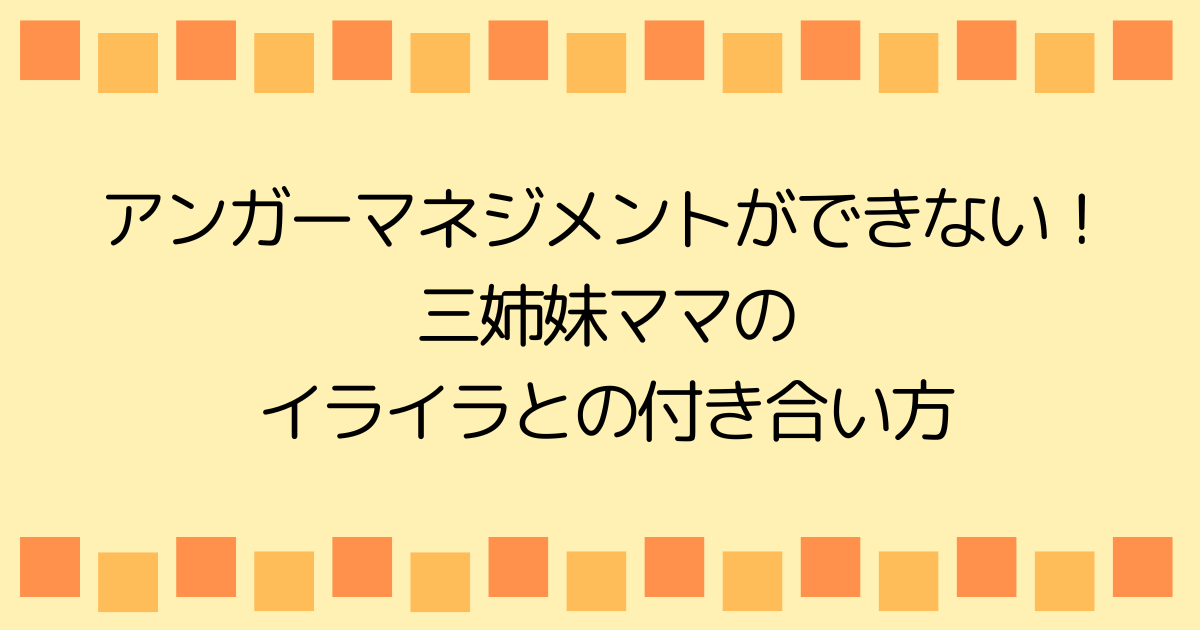
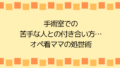
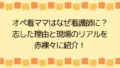
コメント