突然ですが、産後のママで「夫が大好き〜!!」と声を大にして言える人はどれくらいいますか??
わたしは、夫が大好きです!!!そして、夫もわたしが大好きです!😊✨
子どもがいる家庭で、「奥さんが大好き!」と言えるパパはどれくらいいるのかな??
今日は、そんなわたしたち夫婦の関係がなぜ良好なのか??について、わたしと夫の見解を述べたいと思います。
「女性の愛情曲線」って知っていますか?
皆さんは、「女性の愛情曲線」というものをご存知ですか?
これについては、こちらのサイトがわかりやすかったので参考にして見てください。
女性の愛情をかける対象は、出産を機にほとんど「子どものみ」になります。
一旦、夫やパートナーへの愛情は限りなくゼロに近くなる。これはもう本能的なもので仕方ありません。
大事なのは、その後の過ごし方!
「一緒に子育てをした」と感じた女性は、子どもの成長に比例して夫への愛が徐々に復活していきます。
反対に、「1人で子育てをした」と感じた女性は、子どもが大きくなっても夫への愛は低迷したまま。。。
つまり、一旦ゼロになった愛情が元に戻るのかどうかは、「産後のパパの育児への参加具合」にかかっているのです!
「産後の恨みは、一生」。この言葉、本当に真理だと思います。
我が家も長女出産後は険悪なムード
今でこそ夫婦関係が良好だとお互いに言えるわたしたち夫婦ですが、長女出産後は険悪なムードになることも多々ありました。
その理由は、大きく下記の5つです。
初めての育児でお互い手探り状態
1人目の子どもの時は、親のわたしたちももちろん初めての経験をたくさんします。
今なら「そんなにきちっとやらなくても大丈夫!」と思うことでも、わからないが故にきちんとやりすぎ、結局自分を苦しめる。
わたしはパパのやり方ひとつひとつに腹を立て、お互いにうまく長女との生活に馴染めなくて、ピリッとした空気になることはたくさんありました。
泣き声に反応せず夜中起きないパパへの怒り
長女が赤ちゃんの時は、パパは本っ当に泣き声で起きなくて、「なぜこの騒音の中寝られるのか…」と不思議でした。
わたしは「ふぇっ…」って一声あげただけで起き上がり、授乳の姿勢に入るのに、泣かせたまましばらく放置していても、パパは起きない。
普通は寝ているはずの時間に、赤ちゃんの泣き声で起きて、お世話をする。
これって、文字で読むより、想像するより何倍もストレスで、心が削られます。
そこに無神経(なわけではないのだけど、ママフィルターでそう見える)にグースカ寝ているパパを見ると、本当にイライラしました。
睡眠不足によるストレス
言わずもがな、ですね。このブログでは何度もお話ししていますが、「眠れない」ということは本当にストレスで、人格まで変えてしまいます。
睡眠不足で削られた心はナイフのように、周りの人…特に一番身近な家族であるパパに、そのイライラや怒りが向けられてしまうのでした。。
「察してほしい」と「言ってくれなきゃわからない」のすれ違い
これはわたしの1番良くないところです。
「言わなくても、これくらい気づいてほしい」
「考えたらわかるのに…」
と、いつも思っていました。
パパはパパで、
「気づいていないことは言ってほしい」
「1人でモヤモヤしてイライラするのはやめてほしい」
と思っていたそうです。
わたしは、きちんと言葉にして相手に伝えることが足りず(もちろん、言い方に配慮することも忘れずに!)、パパはタスクを繋げて考えることがあの頃は足りなかったと今は思っています。
行きすぎた「子どもファースト」
ご飯中でも、家事の途中でも、泣かせておくことができずに、とにかく長女が泣いたら即座に対応していました。
泣き叫ぶ長女を抱っこしながら、急いでご飯を食べたり、
お腹が痛くても泣いていたら自分が我慢する。
長女を産んだあとは、そんな生活でした。
パパの意見:当事者意識が足りなかった
長女を出産した当時のことをパパに聞いてみると、「妊娠・出産や育児のことを❝自分のこと❞として考えられていなかった」と返ってきました。
女性は妊娠したときから、約10か月お腹で子どもを育て、産後すぐからお世話が始まるのに対して、パパは体調の変化はなく、産休に入ったり出産があったり…と大きく生活が変わることもありません。
産後すぐは入院していて、赤ちゃんのお世話にはどうしてもママ以上に関わることはできないし、里帰りしているとどうしてもお世話の中心はママになってしまう。
産まれて、一緒に生活し始めて、ようやく少しずつ「父親になった」「子どもが産まれた」という自覚が芽生えたそうです。
妊娠や出産、赤ちゃんへのママとの意識の温度差が、夫婦関係をギスギスさせる一因になっていました。
threadで聞いた、産後夫へイライラするとき
threadでも、産後のママに夫にイライラする瞬間について質問してみました。
そして、以下の回答がありました!ご協力いただいた方々、感謝致します😊✨
どれも、「わかるわぁ〜」と激し目に首肯しながら読ませていただきました。
2人目以降のわたしたちの育児
長女出産後はピリついていた我が家ですが、次女・三女の出産後は大きな問題はなく、仲良く過ごせています!
そんなわたしたち夫婦、何が長女の産後と違うのか?主に以下の6点です。
妊娠、出産、育児について経験がある
次女の妊娠期間から、パパは本当にわたしの体調を理解してくれて、いつも気遣ってくれました。
次女出産後は、赤ちゃんのお世話は一通りできるところからお互いがスタートできたので、そこに関する不安は皆無。
やっぱり、経験があるのとないのとでは心の余裕がぜんぜん違う、とこのとき改めて感じました。
とにかく家族ファーストでパパが動いてくれた
もちろん長女のときもでしたが、うちのパパは本当に家族ファースト!
次女のときも育休や、仕事復帰後の残業免除、土曜出勤をなるべく少なくするなど、自分から積極的に「こうしたらいいかな?」と提案してくれました。とってもありがたかった!
赤ちゃんのお世話も、もちろんそうです。
授乳しようかな、と思えば「ミルクは◯mlでいい?」と聞いてくれるし、
うんちが出たな、と思えば「俺がおむつ替えやるからいいよ」と率先してやってくれるし、
長女と次女が「外で遊びたい!」と言えば、二つ返事で連れ出してくれるし。
あげればキリがないですが、とにかく家族・子どもたちファーストに動くことに磨きがかかっています!
赤ちゃんの泣き声に反応できるように進化
長女の時は全く泣き声に気づかなかったパパですが、次女の時は完母でしたが、夜中わたしが授乳で起きるたびに起き上がり、おむつを替えてくれ、わたしの話し相手になってくれました!
三女は夜間はミルクをあげているので、一晩ずつ交代で見ていますが、ちゃんと起きて1人でお世話してくれています。
「男の人は赤ちゃんの泣き声に反応しない」という説もありますが、「本人のやる気も関係ある!」とうちのパパは断言していました👏
赤ちゃんを泣かせておく余裕ができた
あんなに赤ちゃんを泣かせておけなかったわたしですが、物理的に手が足りないときなどは泣かせておけるようになりました。
家事でそばを離れる時は、離れる前に抱っこしたり触れ合って、「大好き」「このあと少し離れるけど、待っていてね」と伝え、その最中に泣いてしまっても遠くから声をかけて、少し置いておくことができるようになりました!成長!
やってほしいことははっきり言うようになった
「察してほしい」はやっぱり良くない!と思い、次女の産後からは「これやって」「こういうやり方でやってほしい!」ときちんと言葉にするようにしました。
やってほしいことがちゃんと伝わると、パパはすぐにやってくれ、お互いのストレスが減りました。
ただ、言い方に配慮は絶対必要です!強い言葉で、感情的に伝えてもあまり効果的ではありません。
お互いが気持ちよく過ごすために、柔らかい言葉で、やってほしいことは正確に伝わるように考えなければいけないと思います。
パパがタスクを線でやってくれるようになった
もともと子どものお世話は率先してやっていたパパですが、以前は「やって」と言われたことをやっている感じでした。
でも、次女の産後からは言わなくても家事やお世話を繋げてやってくれ、本当に助かっています。
たとえば、お出かけの準備。おむつポーチをカバンに入れる前に、おむつの残数と、今日の気候に合った着替えが入っているかを確認。外出が長くなりそうだったら、言わずもがな三女が今飲む量のミルク(ここが大事!)と持ち運びに適した哺乳瓶を準備して、入れて準備する。
文字に起こすと簡単そうに見えますが、この一連の準備を赤ちゃんや他の兄弟を見ながらひとりでやるって、結構大変です。
マミーブレインが止まらないわたしを、とっっても助けてくれます😊
1人目をこれから迎えるパパにやってほしいこと
非常に良好な夫婦関係で、3人目の育休を楽しんでいるわたしたち夫婦から、これからパパになる人に育児を楽しんでもらうために、ぜひやってほしいことをお伝えしますね。
パパの意見:子どもよりもママファースト
パパは、とにかく子どもよりも「ママがどうしてほしいか?」を考えることが大事!と我が家のパパは言っていました。
うんうん、確かに。我が家のパパは、わたしの気持ちを1番に考えて動いてくれているな、と感じます。
わたしは、とにかく子どもたちのことを1番に考えています。
食事やお風呂などの普段の世話はもちろん、学校や保育園の準備、必要なもの、普段の生活の中で行動を注意したり、逆に褒めたり…そのわたしの考えを読まれているな、と思うことは三女の育休中の今、たくさんあります。
ママを優先することで、結果的に子どもたちのためになる。
そのことを我が家のパパは本当に大事にしてくれているな~と毎日感じています!
妊娠、出産の正常な経過を知ること
ママは妊娠したそのときから、自分の体の変化、いろいろな不安を感じます。そのときに一緒のレベルで話ができるように、妊娠、出産の正常な経過をまず知ってください。
今はいろいろな妊娠中に活用できるアプリがありますが、わたしは「トツキトオカ」をダウンロードすることをおすすめします。
その妊娠週数の経過のこと、ママの変化、胎児の様子について詳しく読むことができるので活用してみてください。
妊娠中に、産後のママの状態を知ること
産後のママは、周りの人が思う以上にダメージを受けています。それがどんな状態なのか知り、自分がどういう風に動けばその負担が軽くなるのか、妊娠中から考えてください。
ママと同じレベルで家事ができるようにしておく
上記の通り、産後のママは予想以上のダメージを受けています。赤ちゃんのお世話で精一杯で、正直なところパパのことまで構っている余裕はありません。
我が家のパパは、料理は一切できませんでしたが、妊娠中つわりで体調の悪いわたしに代わって料理をするようになり、今は交代制で食事当番をしています。
やる気があって、実際にやってみれば、なんでもできるようになります。今からでも遅くないので、できない人は家事は一通りできるようにしておいた方が良いです!
子どものこと、ママのことを気にかけること
「当たり前じゃん!」と思われるかもしれませんが、これはとても大事です!
思うだけじゃなくて、言葉にしてママに聞くこと!
健診の日だったのに何も聞かれなかったり、赤ちゃんのお世話で悩んでるのに「わかんない」「任せるよ」って言われたりすると、ママが「あなたも親だよね?」と思ってしまうかもしれません。
子どもや、胎児、ママのことに興味を持って、たくさん話をしてくださいね。
SOSを見逃さないこと
今年はママが赤ちゃんを手にかけてしまうニュースが多く聞かれた気がします。
そして、パパは「妻の様子が変だった」と言っている事件もありました。
わたしも、長女が赤ちゃんの頃は精神的な限界を迎えて「もう無理。早く帰ってきて」と、仕事中のパパに泣きながら連絡したことがあります。
ママは、常に睡眠不足、話の通じない赤ちゃんとの生活でストレスフル。
そこに産後のホルモンバランスの変化が加わると、自制が効かないほど感情が揺らぐことは多々あります。
普段一緒にいるパパが「変だな」と思っただけで、理由は十分です。仕事を休んだり、どうしても無理なら産後ケア施設や病院に行くことを勧めたり、とにかくSOSを見逃さないでください。
最後に
夫婦関係が良好で、2人で育児に取り組めると、幸福感はグンッと高まります。
大好きで夫婦になった人と、せっかくならいつまでも楽しく仲良く暮らしたいですよね😊
子どもが少し大きくなってから、「2人で育児ができた」と感じられるように、我が家も育児に奮闘したいと思います!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*’▽’)
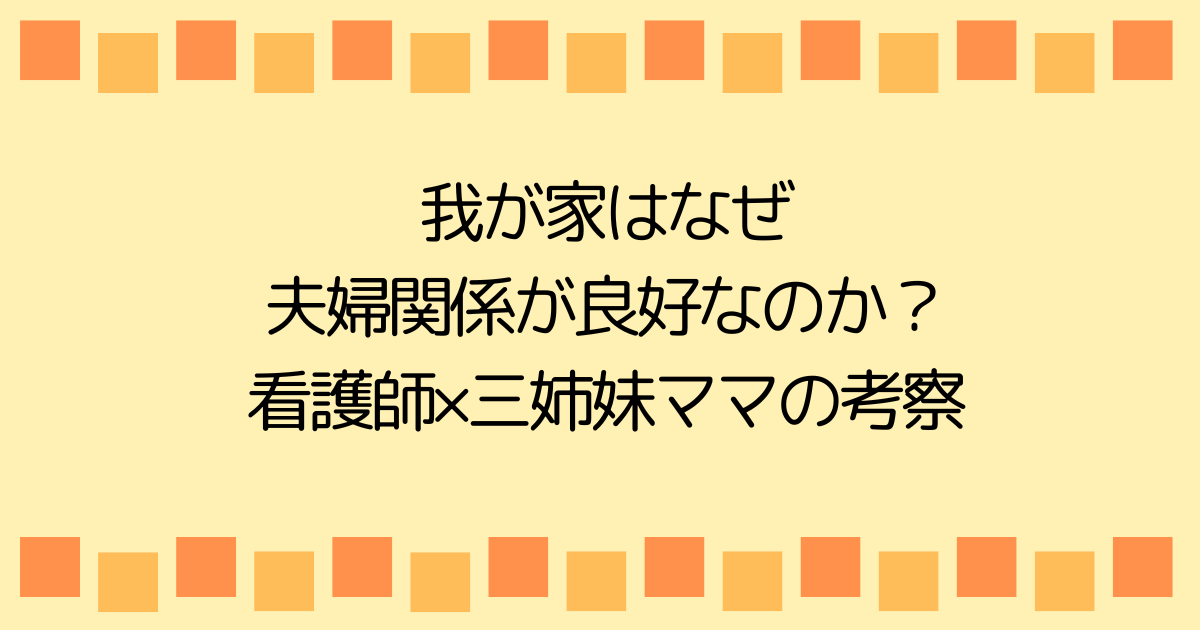
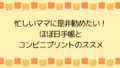
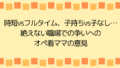
コメント