「オペ室では働きたくない!!」という看護師さんたちに理由を聞くと、いろいろな意見をいただきました!ありがとうございます!
その中にあった、麻酔科医との関わりや麻酔導入について、今日はお話ししたいと思います。
麻酔科医やその他の医師との関わり
オペ室は、特に医師と関わることが多い部署です。
言わずもがなですが、「手術」を行うのは医師であり、オペ室で働くスタッフの仕事は「手術に関わる診療の補助」であるためです。
看護師のもう一つの業務である「療養上の世話」は皆無と言っても過言ではありません。
術前、術中、術後のそれぞれの場面で、医師とどういう関わりが必要になるか、以下に記載していきたいと思います。
術前
手術のオーダーが医師から入力され、担当者が振り分けられると、器械出しも外回りもそれぞれ準備を進めます。
コンスタントに行われている術式であれば、特別なことがなければ医師に確認することは少なく、ルーティンワークがほとんどです。
重要なのは、症例数が少ない術式や新しい機種の器械を使うときなど、いつもと違うことをするとき。
どういった手技で手術を進めていくのか、追加で用意しておく器械はあるのか、バックアップの器械は何があるのか、準備しておく薬剤はあるのか…確認することはその手術によって違います。
これは器械出しだけではなく、外回りも同様です。
いつもと違う神経ブロックをする場合や、いつもは使用しない薬剤の指示がある場合は、麻酔科医へ希釈など細かく確認する必要があります。
患者さん入室〜術中
麻酔導入時の薬剤投与は、麻酔科医の口頭指示に基づいて、看護師が行うことが多いです。
病棟のように指示書はありません。
麻酔導入は、麻酔科医と密に連携をとり進めていく必要があります。
手術が始まると、術野の動きに合わせて器械出しも外回りも動いていくことになります。
必要物品を早めに執刀医へ確認して準備しておいたり、患者さんのバイタルサインの変化に合わせて麻酔科医に指示を仰いで薬剤を準備したり…何をするにも医師とのコミュニケーションは必須です。
手術終了後〜患者さん退室
手術が終わると、患者さんの麻酔からの覚醒・退室に向けてバタバタと処置をしていきます。
ドレーンをクランプする場合は開放時間を確認したり、
体位固定や手術器械による褥瘡や裂傷などがあれば執刀医にも一緒に確認してもらって追加の指示を仰いだり、
麻酔科医に使用薬剤や処置を確認したり…
とにかく、患者さんが退室するまでは、誰かかれか医師とは一緒に行動します。
どの場面でも必然的に、医師とのコミュニケーションは必要となってきますね。
麻酔導入時うまく麻酔科医と連携するには?
麻酔科医は、オペ室以外の場所では密に関わることが少ない医師だと思います。
その代わり、オペ室では1番長い時間を一緒に過ごす医師です。連携がうまくできるに越したことはありません。
そのために、わたしが大切にしていることを3点お伝えします。
基本の麻酔導入の流れをまずは覚える!
麻酔導入時の流れは、だいたい決まっています。
まずはモニター装着してバイタルチェック、点滴ルート刺入部の確認、マスクフィットの確認、酸素化、鎮静剤投与、マスク換気、筋弛緩薬投与…
この基本の流れをまずは覚えることが大事!
麻酔方法は何パターンもあるし、薬剤のことや神経ブロック、エピなどなど盛り沢山なのですが、頑張って流れを覚える。
厳しいことを言うと、それができていないと連携どころの話ではないです。
それぞれの麻酔科医のクセを覚える!
麻酔方法は、麻酔科医の数だけあると言っても良いとわたしは考えています。
同じ大学、同じ医局出身だからと言って、全く同じやり方をしている人はおそらくいません。
必ずどこかにこだわりがあるし、クセがあります。
まずは、そこを徹底して覚えること。
わたしは麻酔科医ごとのメモを作っていて、新しいことは術中の少し時間があるときに走り書きし、業務が終わってから理由を調べるようにしています(これは執刀医に対しても同じです)。
わたしの今働く病院には7人くらい麻酔科医がいますが、同じ手術の同じ麻酔をかける場合でも、やっぱり少しずつ違います。
とにかく、その麻酔科医のやり方を覚える。
そして、「どうしてそのやり方なのか」自分なりに調べて勉強してみる。
これが大切なことだと思います。
麻酔科医に直接聞いてみる
看護師向けの参考書だと、どうしても解決できない疑問にぶつかることもありますよね。
そういうときは、聞けるチャンスがあれば麻酔科医本人に聞いてみることも大切だとわたしは考えています。
大事なのは、「自分で調べて勉強してみてから」!!
何も努力せず、いきなり答えを求めてはいけません。
術中動きがなく、患者さんのバイタルも落ち着いていると、案外いろいろ教えてくれる先生は多いです。
そして麻酔科医に聞くと、本当に勉強になるし理解が深まります。
ただし教えてもらったことは必ず次の機会に活かすこと。「あの時教えたのにな」と思われないようにしましょう。
こちらから歩み寄れば応えてくれる!
あまりに不勉強でやる気がない人を除いて、こちらが一生懸命勉強してやる気があってコミュニケーションを取っていけば、麻酔科医も協力してくれるようになります。
(でも一部、どうやっても協力の得られない人はいます。そういう人のことは「寂しい人だな」と思って、必要以上の関わりを避けましょう)
術野への対応で手が離せない時、そっと手を貸してくれたり、
どうしても部屋の外へ出なければならない時、「行ってきていいよ」と言ってくれたり、
とにかく、同じ手術室で働く同僚として、良い関係を築くことができるのは間違いないです!
「いやだな」「喋りたくないな」と思わず、まずは麻酔のことから話をしてみましょう😆
最後に
麻酔科医とうまく連携するためには、
これが大切なことです!
オペ室では、本当に長い時間を麻酔科医と一緒に過ごします。
どうせなら良い関係を築いていきたいですよね。
人間関係は、まずは「相手を知りたい」と思うところから始まるとわたしは思います。それは仕事の上の関係でも同じこと。
みんなで気持ちよく働けるように、良い関係を医師とも築いていけたらいいなと思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*’▽’)
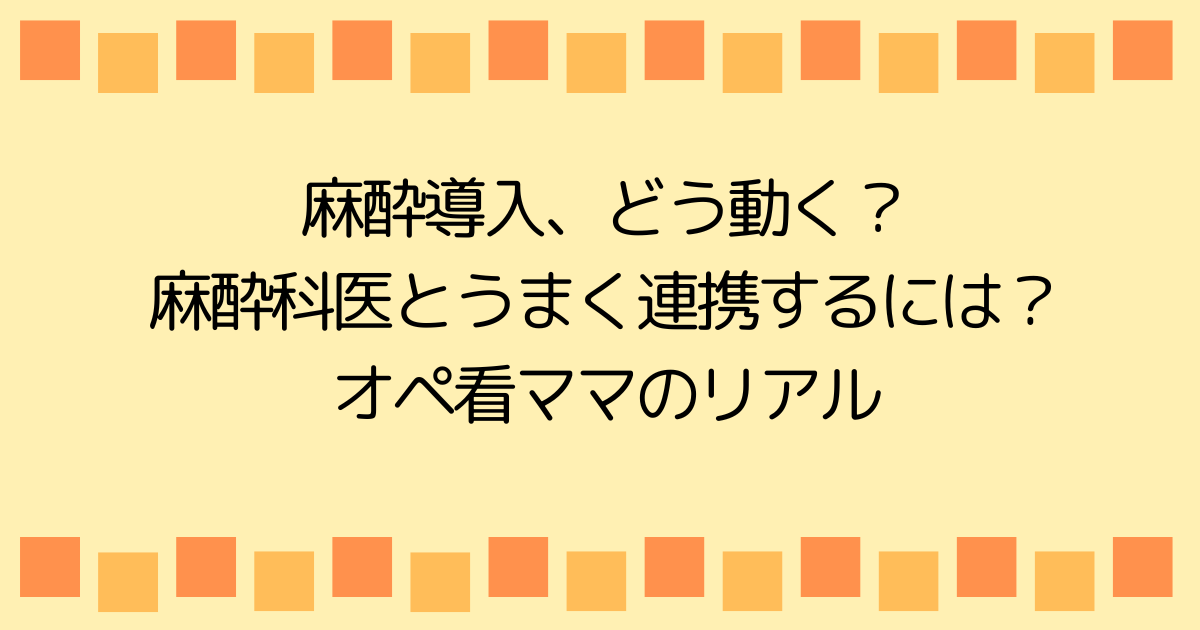
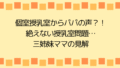
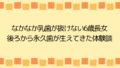
コメント