妊娠、出産、育児…ここ数年で、わたしが身をもって経験してきたことです。
そして、経験しなければわからないこと…「親が子どもを思う気持ち」は、知識や自分の子どもとしての経験では知っていたけれど、実際どういう気持ちなのかは親になって初めてわかったことです。
今日は、自分が出産して、親になって、仕事中の姿勢が変わったことについて、お話したいと思います。
子どもは手術や処置を嫌がって当たり前
まず、「麻酔導入」とは一般的に全身麻酔をかけ、手術に臨める状態にすることです。
薬剤によって意識を消失させ、呼吸を助ける管を口または鼻から挿入(=挿管)したり、手術に応じて神経ブロックや硬膜外麻酔などを行うことを指します。
子ども…と言っても幅広いですが、主に未就学児〜小学校低学年くらいの子たちは、とっても手術を怖がるし、その感情をストレートに医療者や保護者にぶつけます。
手術は大人にとっても「非日常的」なことで、「よくわからない未知の世界」の話です。
子どもなら尚更恐怖を感じるものだし、やりたくないのが当たり前で、感情をストレートに表現できるのは子どもの特権でもあります。
そういう子どもたちの不安を和らげるために、術前訪問に担当のオペ看が行って話をしてくる、人形などを使って子どもでも理解できるように説明する(=プレパレーションといいます)などの援助をオペ室では行っています。
そして、手術当日のオペ室入室から麻酔がかかって眠ってしまうまで、保護者に一緒にオペ室へ入ってもらう「同伴入室」を行っている施設もあります。
大人の手術との違い
大人と子どもの麻酔導入については、いくつか違う点がありますので説明しますね。
点滴ルートはオペ室で挿入する
一般的に大人の全身麻酔の手術では、術前に病棟で点滴ルートを挿入してきます。
全身麻酔で使用する薬剤は基本的には点滴から投与するものがほとんどだし、麻酔導入後の血圧低下や徐脈に対して素早く対処するために、点滴ルートが必須となるからです。
また、全身麻酔下の手術前には飲食することができない「絶飲食」の時間が必ずあります。
数時間前から水も飲めないので、脱水を起こさないためにも術前に点滴ルートを確保し、点滴しながらオペ室へ入室することが一般的です。
しかし、子どもの場合は少し違います。
施設によるとは思いますが、わたしが勤務してきた病院では未就学児は、オペ室で眠ってから点滴ルートを確保することがほとんどでした。
なぜなら、起きている状態で点滴ルートを確保するこが非常に難しいケースが多いからです。
乳児や幼児は血管が細い上に脂肪組織に覆われているため、もともと大人より点滴ルートの確保は難しいです。
それに加えて「じっとしていてね」など、こちらの指示が通らないこともしばしばあります。
点滴の意味を理解できないことが多いので、せっかく挿入しても抜かれてしまったり…とリスクも大きいです。
そのため、麻酔科医と相談のもとオペ室で眠ってから点滴ルートを確保することが多いのです。
急速導入ではなく緩徐導入が多い
「オペ室で眠ってからって、点滴がないのにどうやって薬で眠らせるの?」と思った人!すばらしい!鋭いです!
まず、全身麻酔のかけ方から説明しますね。
大人の場合は、「急速導入」といって、点滴から鎮静剤(プロポフォールやディプリバンなど)を投与し、素早く意識を消失させる方法が一般的です。
低血圧や徐脈に対しても点滴ルートから対処ができるし、入眠前に酸素化(=純酸素を吸ってもらうこと)と入眠後にマスク換気(=酸素マスクを顔にピッタリ密着させ、麻酔器の呼気バッグを麻酔科医が押して呼吸させること)をしているので、自発呼吸がない挿管時の無呼吸にもある程度耐えられます。
一方で、子どもの場合は点滴ルートがないことが多いため「緩徐導入」が一般的です。
緩徐導入では、酸素マスクから気化器を通した吸入麻酔薬を患者さんに吸わせ、呼吸によって肺から取り込んだ麻酔薬で徐々に意識を消失させます。
オペ室ではよく「スロー導入」「スロー」と呼ばれています。呼吸や循環動体の変動は少なく、泣き叫ぶ子どもでもマスクさえ当てられれば眠らせることができます。
そして眠った後に点滴ルートを確保し、挿管するのが一般的な緩徐導入の一般的な流れになります。
保護者の「同伴入室」を行う施設がある
大人の場合は、手術室へは基本1人で入室してもらいます。付き添いの方は、手術室の前でお別れするのがほとんどです。
しかし、子どもの場合は「同伴入室」といって、麻酔がかかって眠ってしまうまで保護者に一緒に手術室へ入ってもらうことも珍しくありません。
その理由は、子どもの不安軽減のためです。
一緒に入室して、子どもが泣いてしまったり、手術台に横になることが難しければ保護者に抱っこしてもらったままモニター類をつけることもあります。
手術台に横になれたときでも、マスクを当てて眠るまで手を握ったり、声をかけてもらったりしても構いません。
とにかく、子どもが少しでも不安なく手術に臨めるように、保護者の方にも一緒に援助してもらいます。
麻酔がかかって患児が眠れば、保護者の方には退室してもらって、手術が終わるまで病室やディルームで待っていてもらいます。
同伴入室する保護者に説明すべきこと
自分が出産を経験して親になってからは、次のようなことを術前訪問や、実際の麻酔導入時に説明するようにしています。
泣いて暴れてしまう場合は体を押さえる場合がある
親になって思うことは、「我が子の泣き声や助けを求める言葉は想像以上に親の心をえぐる」ということ。
子どもが産まれる前は、麻酔導入時に抑制(=体を押さえること)することは「仕事の一環」でしかありませんでした。
安全に麻酔をかけるために、必要なこと。仕方ないこと。
わたしの意識はいつも「患児」へ向いていて、保護者の方はどこか置いてきぼりにしていたな、と今は思います。
麻酔をかけるとき、子どもは皆さんが想像している以上に泣くし、嫌がる子が多いです。
「ママ、助けて!」
「ママ、やめさせて!帰りたい!」
「やだ!やめて!来ないで!」
こういう言葉を発する子も多いし、ただただ嫌がって泣き叫ぶ子もいます。こんなときは、わたしたち看護師や麻酔科医は安全のために複数人で泣いて嫌がる子どもを押さえなければならないのです。
ただ親としては、頭では「手術は必要なこと」「体を押さえるのは安全のため」とわかっていても、泣き叫んで大人に押さえつけられる我が子を見るのは本当につらいし、「代わってあげられたら」と思うし、とにかく結構ダメージを受けるだろうなと思います。
子どもが産まれて自分が親の立場になってからは、術前訪問で
「安全のために、身体を押さえる場面もあります。お母さんもつらいと思うけど、一緒に頑張りましょう」と説明してくるようになったし、
実際に麻酔をかける場面でも「動いてしまうと危ないので、身体を押さえさせてもらいますね。」と声をかけるようになりました。
緩徐導入では興奮期があること
酸素マスクから吸入麻酔薬を投与する緩徐導入では、麻酔薬の濃度が低いときに「興奮期」が起きる場合が多いです。
興奮期とは、外界からの刺激に鈍くなり自制心が喪失することで、体動が急に激しくなったり叫んだりすることを言います。こちらからの言葉は聞こえていないし、意思疎通はできません。
麻酔への知識がない一般の方が見ると、「これは我が子…?」とびっくりするかもしれません。
急に暴れたり、大きな声を出したりするのですから当然です。いつもと違う、我が子のこういう姿、結構保護者の方はダメージを受けるのではないかと思います。
加えて、興奮期には思いがけないほど強い力で暴れることもあるため、看護師も緊張します。
強い力で、何人もの大人に押さえつけられる我が子を見るのは本当につらいことだと思います。
なので自分が出産してからは、術前訪問や実際の麻酔導入時に
「薬の影響で、本人の意思とは関係なく暴れてしまうことがあります。安全のために、こちらで押さえさせてもらう場面がありますので、よろしくお願いします」
「今麻酔がかかって、少し暴れてしまうので身体を押さえさせてもらいますね。正常な経過ですから、安心してください」
と声をかけ、説明するようになりました。
同伴入室を終えたら保護者にも労いの言葉を
同伴入室をしてもらい、麻酔にかかって患児が入眠すると保護者の方には退室してもらう施設が多いかと思います。
オペ看としては、このあとに点滴ルートの確保や挿管介助、場合によっては神経ブロックを行ったり、手術に向けた体位固定を進めていくため、忙しい本格的な麻酔導入の始まりです。
が、保護者の方は手術への不安はもちろんある中で、手術室という非日常的な空間で、普段と違う我が子を目の当たりにし、少なからずショックを受けています。
なので、わたしが保護者の方を手術室の入り口まで案内する係になったときには
「○○ちゃん、頑張っていましたね。お母さんもお疲れ様でした。」
「責任をもって、お預かりします。」
と、お母さんに対する労いの言葉を忘れずに、患児の頑張りにも声をかけます。責任をもって患児を預かることも一緒に伝えます。
患児の麻酔導入が終わって、退室するときに涙を流すママは多いです。我が子の心配、麻酔導入する姿、自分の無力感…きっといろいろな気持ちがごちゃ混ぜになって流れる涙だと思います。
涙を流されていれば、ティッシュを渡したり背中をさすったり…という援助も必要になってくるかもしれません。
とにかく、患児はもちろんのこと、保護者の方も手術・麻酔によって少なくないショックを受けているということを、オペ室で働くスタッフは知るべきだと考えます。
自分がその立場になって、わかることってたくさんある
以上が、わたしが親になってみて初めてわかった本当の「保護者の気持ち」と、それに対して必要だと感じる援助です。
自分の娘たちが手術を受けることになったら…
手術や麻酔をわかっているわたしでも、「代わってあげたい」と思うし、頑張っている我が子を見たら涙を流す確信があります…
一般の方で、手術や麻酔が未知のものだったら、不安や心配はことさらに大きいでしょう。
そのことを忘れずに、今後の自分の手術看護に、親になった経験を活かしていきたいなと強く思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*’▽’)
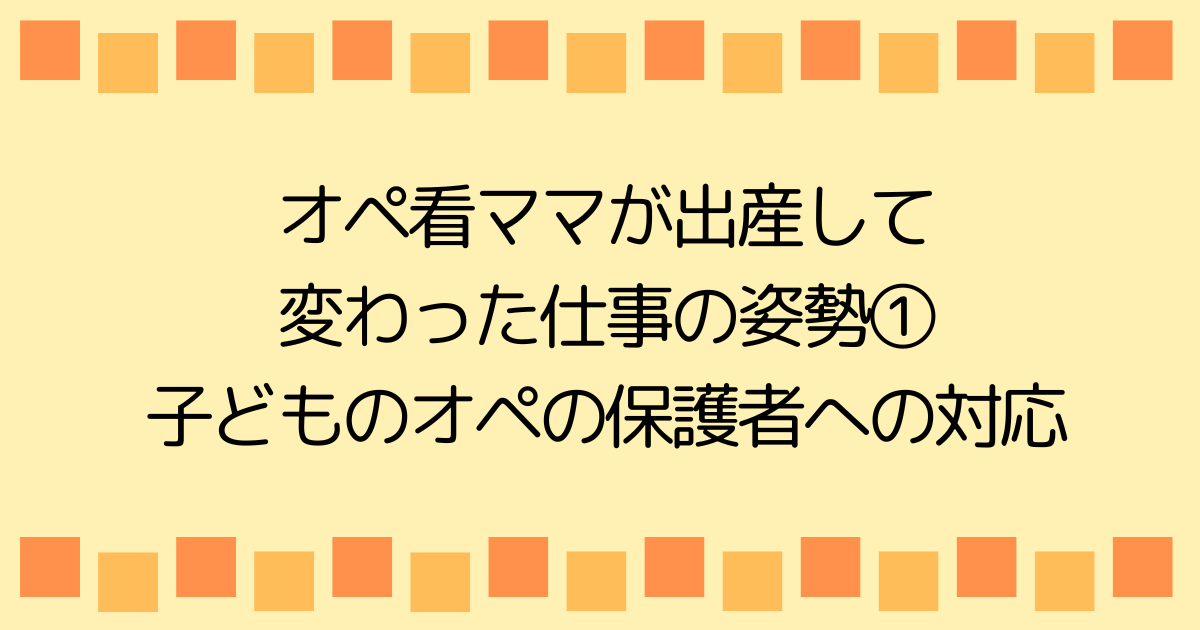
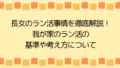
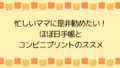
コメント